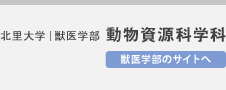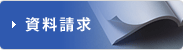広がる学び
[コラム] 動物介在活動・療法の現状と展望
動物介在活動および動物介在療法の先進国である欧米では、実に様々なかたちで動物たちが活躍しています。このコラムでは、動物介在活動・療法で最もよく登場するイヌに着目して、海外での研究例や実例を紹介するとともに、国内における動物介在活動・療法の現状と展望について記述したいと思います。
米国では1970年代から刑務所などで受刑者への矯正プログラムとして動物介在療法が実施されています。そのひとつとして、重犯罪者用女子刑務所で受刑者がイヌの世話、トリミング、獣医師の助手などを通して動物収容施設のイヌを訓練し、一般の家庭犬として復帰させる取り組みがありました。受刑者は自尊心を向上させ、社会貢献ができたという満足感を得るとともに、受刑者の適切な社会行動が増えたといった効果がありました。一方で、飼い主に捨てられて施設に収容されたイヌの方は、この取り組みによって新たな飼い主に出会う機会を得ました。この取り組みはヒトと動物の双方が幸せになった良い例だといえるでしょう。
 イヌを用いて成果を挙げた例として、同様に米国の精神科小児病棟で実施されたもうひとつの取り組みも紹介しましょう。この病院では、病院スタッフがイヌの食事、運動、グルーミングといった日常的な世話をし、患者もその世話に参加できるようになっていました。この療法では、イヌの介在によっていわゆる施設的な環境になりがちな病院の環境が家庭環境に近いものなった、あるいは患者が病院スタッフに親近感を持ったなどの効果のほか、特に大人に話すことは危険だと学習してしまっていた子どもが、イヌに向かって話しかけていた行動が観察されています。イヌにとっては、患者の心身にどんな障害があろうと、患者がどんな服を着ていようと、どんな体型であろうと関係ありません。患者はこれまで他の人からはあまり得られなかった無条件の受容をイヌから得ることができました。さらに、患者はイヌに乱暴をするとイヌが来なくなってしまうという事実を学習し、患者による乱暴な行動が減少するといった成果もありました。
イヌを用いて成果を挙げた例として、同様に米国の精神科小児病棟で実施されたもうひとつの取り組みも紹介しましょう。この病院では、病院スタッフがイヌの食事、運動、グルーミングといった日常的な世話をし、患者もその世話に参加できるようになっていました。この療法では、イヌの介在によっていわゆる施設的な環境になりがちな病院の環境が家庭環境に近いものなった、あるいは患者が病院スタッフに親近感を持ったなどの効果のほか、特に大人に話すことは危険だと学習してしまっていた子どもが、イヌに向かって話しかけていた行動が観察されています。イヌにとっては、患者の心身にどんな障害があろうと、患者がどんな服を着ていようと、どんな体型であろうと関係ありません。患者はこれまで他の人からはあまり得られなかった無条件の受容をイヌから得ることができました。さらに、患者はイヌに乱暴をするとイヌが来なくなってしまうという事実を学習し、患者による乱暴な行動が減少するといった成果もありました。
ところで、イヌなどと接していると私たちの健康は本当に維持・増進されるのでしょうか。米国の研究結果ですが、高齢者におけるイヌの飼育の有無と通院回数との関連を調べた興味深いデータがあります。その結果によれば、イヌ非飼育者の通院回数が年間10.37回であったのに対し、イヌ飼育者の通院回数は年間8.62回であったという結果でした。これは、イヌを飼育する高齢者の通院回数が、イヌを飼育しない高齢者に比べて年間1.75回少ないことを示しています。この報告を受けて、米国 National Institute of Health(NIH) はイヌ飼育により医療費を節減できるとして、予防医学の観点からイヌの社会的役割に注目しています。
こういった研究成果が蓄積されてきたなかで、今後欧米ではますます動物介在活動・療法への関心が高まり、その取り組みも進められてゆくことでしょう。これとは対照的に、残念ながらわが国では動物介在活動・療法の社会的認識は現在のところ高くありません。これには、わが国ではヒトと動物の関係が欧米と比較して希薄であった歴史が関係しているのかもしれません。農耕を主として生活してきたわれわれと違って、欧米ではヒトが家畜と密接にかかわりながら生活してきた歴史があります。そのため、欧米諸国の人々は動物の飼育、とりあつかい、および利活用といった畜産業を得意としてきました。戦後わが国の畜産業は欧米のシステムを取り入れてめざましいスピードで発展してきました。集約化と効率化を徹底し、今やわが国の動物生産技術は欧米に肩を並べるレベルに達しましたが、はたしてヒトと動物の心の交流は十分になされているでしょうか?
わが国の動物介在活動・療法はまさに歩みだしたところといえます。 福祉施設あるいは教育施設での動物介在活動は少しずつ実施され始めています。しかし、病院など医療施設での動物介在療法の実施に向けては、まだまだクリアーしなくてはならない諸問題が残っています。動物をヒトの心のケアに活用するためには、ヒトの心に関しても深く知っておく必要があります。北里大学の実施する農医連携教育では、動物介在療法を行う上で最低限必要となる精神科分野の知識を習得し、精神障害を持つ患者への対応やコミニュニケーション法を学んだ上で、医師以外の医療職種とコミュニケーションする方法も学びます。わが国で動物介在療法を展開するためには、医療施設サイドからも問題点を解決する視点をもつことが重要となります。日頃から学習している動物資源科学分野の知識や技術に加え、精神医学領域での専門知識と技術を身につけておけば、動物介在活動・療法に携わる人にとって鬼に金棒といえるでしょう。物質的には豊かになった一方、様々なストレス要因に囲まれ、さらには少子高齢化がすすむわが国において、近い将来、動物介在活動・療法の需要が高まることは明らかです。病棟で、患者が特別にトレーニングされた動物と心を通わせている風景のある成熟された将来に向けて、われわれは農と医の両面から準備を進めていく必要があります。
福祉施設あるいは教育施設での動物介在活動は少しずつ実施され始めています。しかし、病院など医療施設での動物介在療法の実施に向けては、まだまだクリアーしなくてはならない諸問題が残っています。動物をヒトの心のケアに活用するためには、ヒトの心に関しても深く知っておく必要があります。北里大学の実施する農医連携教育では、動物介在療法を行う上で最低限必要となる精神科分野の知識を習得し、精神障害を持つ患者への対応やコミニュニケーション法を学んだ上で、医師以外の医療職種とコミュニケーションする方法も学びます。わが国で動物介在療法を展開するためには、医療施設サイドからも問題点を解決する視点をもつことが重要となります。日頃から学習している動物資源科学分野の知識や技術に加え、精神医学領域での専門知識と技術を身につけておけば、動物介在活動・療法に携わる人にとって鬼に金棒といえるでしょう。物質的には豊かになった一方、様々なストレス要因に囲まれ、さらには少子高齢化がすすむわが国において、近い将来、動物介在活動・療法の需要が高まることは明らかです。病棟で、患者が特別にトレーニングされた動物と心を通わせている風景のある成熟された将来に向けて、われわれは農と医の両面から準備を進めていく必要があります。
担当 動物行動学研究室
講師 松浦 晶央
米国では1970年代から刑務所などで受刑者への矯正プログラムとして動物介在療法が実施されています。そのひとつとして、重犯罪者用女子刑務所で受刑者がイヌの世話、トリミング、獣医師の助手などを通して動物収容施設のイヌを訓練し、一般の家庭犬として復帰させる取り組みがありました。受刑者は自尊心を向上させ、社会貢献ができたという満足感を得るとともに、受刑者の適切な社会行動が増えたといった効果がありました。一方で、飼い主に捨てられて施設に収容されたイヌの方は、この取り組みによって新たな飼い主に出会う機会を得ました。この取り組みはヒトと動物の双方が幸せになった良い例だといえるでしょう。
 イヌを用いて成果を挙げた例として、同様に米国の精神科小児病棟で実施されたもうひとつの取り組みも紹介しましょう。この病院では、病院スタッフがイヌの食事、運動、グルーミングといった日常的な世話をし、患者もその世話に参加できるようになっていました。この療法では、イヌの介在によっていわゆる施設的な環境になりがちな病院の環境が家庭環境に近いものなった、あるいは患者が病院スタッフに親近感を持ったなどの効果のほか、特に大人に話すことは危険だと学習してしまっていた子どもが、イヌに向かって話しかけていた行動が観察されています。イヌにとっては、患者の心身にどんな障害があろうと、患者がどんな服を着ていようと、どんな体型であろうと関係ありません。患者はこれまで他の人からはあまり得られなかった無条件の受容をイヌから得ることができました。さらに、患者はイヌに乱暴をするとイヌが来なくなってしまうという事実を学習し、患者による乱暴な行動が減少するといった成果もありました。
イヌを用いて成果を挙げた例として、同様に米国の精神科小児病棟で実施されたもうひとつの取り組みも紹介しましょう。この病院では、病院スタッフがイヌの食事、運動、グルーミングといった日常的な世話をし、患者もその世話に参加できるようになっていました。この療法では、イヌの介在によっていわゆる施設的な環境になりがちな病院の環境が家庭環境に近いものなった、あるいは患者が病院スタッフに親近感を持ったなどの効果のほか、特に大人に話すことは危険だと学習してしまっていた子どもが、イヌに向かって話しかけていた行動が観察されています。イヌにとっては、患者の心身にどんな障害があろうと、患者がどんな服を着ていようと、どんな体型であろうと関係ありません。患者はこれまで他の人からはあまり得られなかった無条件の受容をイヌから得ることができました。さらに、患者はイヌに乱暴をするとイヌが来なくなってしまうという事実を学習し、患者による乱暴な行動が減少するといった成果もありました。ところで、イヌなどと接していると私たちの健康は本当に維持・増進されるのでしょうか。米国の研究結果ですが、高齢者におけるイヌの飼育の有無と通院回数との関連を調べた興味深いデータがあります。その結果によれば、イヌ非飼育者の通院回数が年間10.37回であったのに対し、イヌ飼育者の通院回数は年間8.62回であったという結果でした。これは、イヌを飼育する高齢者の通院回数が、イヌを飼育しない高齢者に比べて年間1.75回少ないことを示しています。この報告を受けて、米国 National Institute of Health(NIH) はイヌ飼育により医療費を節減できるとして、予防医学の観点からイヌの社会的役割に注目しています。
こういった研究成果が蓄積されてきたなかで、今後欧米ではますます動物介在活動・療法への関心が高まり、その取り組みも進められてゆくことでしょう。これとは対照的に、残念ながらわが国では動物介在活動・療法の社会的認識は現在のところ高くありません。これには、わが国ではヒトと動物の関係が欧米と比較して希薄であった歴史が関係しているのかもしれません。農耕を主として生活してきたわれわれと違って、欧米ではヒトが家畜と密接にかかわりながら生活してきた歴史があります。そのため、欧米諸国の人々は動物の飼育、とりあつかい、および利活用といった畜産業を得意としてきました。戦後わが国の畜産業は欧米のシステムを取り入れてめざましいスピードで発展してきました。集約化と効率化を徹底し、今やわが国の動物生産技術は欧米に肩を並べるレベルに達しましたが、はたしてヒトと動物の心の交流は十分になされているでしょうか?
わが国の動物介在活動・療法はまさに歩みだしたところといえます。
 福祉施設あるいは教育施設での動物介在活動は少しずつ実施され始めています。しかし、病院など医療施設での動物介在療法の実施に向けては、まだまだクリアーしなくてはならない諸問題が残っています。動物をヒトの心のケアに活用するためには、ヒトの心に関しても深く知っておく必要があります。北里大学の実施する農医連携教育では、動物介在療法を行う上で最低限必要となる精神科分野の知識を習得し、精神障害を持つ患者への対応やコミニュニケーション法を学んだ上で、医師以外の医療職種とコミュニケーションする方法も学びます。わが国で動物介在療法を展開するためには、医療施設サイドからも問題点を解決する視点をもつことが重要となります。日頃から学習している動物資源科学分野の知識や技術に加え、精神医学領域での専門知識と技術を身につけておけば、動物介在活動・療法に携わる人にとって鬼に金棒といえるでしょう。物質的には豊かになった一方、様々なストレス要因に囲まれ、さらには少子高齢化がすすむわが国において、近い将来、動物介在活動・療法の需要が高まることは明らかです。病棟で、患者が特別にトレーニングされた動物と心を通わせている風景のある成熟された将来に向けて、われわれは農と医の両面から準備を進めていく必要があります。
福祉施設あるいは教育施設での動物介在活動は少しずつ実施され始めています。しかし、病院など医療施設での動物介在療法の実施に向けては、まだまだクリアーしなくてはならない諸問題が残っています。動物をヒトの心のケアに活用するためには、ヒトの心に関しても深く知っておく必要があります。北里大学の実施する農医連携教育では、動物介在療法を行う上で最低限必要となる精神科分野の知識を習得し、精神障害を持つ患者への対応やコミニュニケーション法を学んだ上で、医師以外の医療職種とコミュニケーションする方法も学びます。わが国で動物介在療法を展開するためには、医療施設サイドからも問題点を解決する視点をもつことが重要となります。日頃から学習している動物資源科学分野の知識や技術に加え、精神医学領域での専門知識と技術を身につけておけば、動物介在活動・療法に携わる人にとって鬼に金棒といえるでしょう。物質的には豊かになった一方、様々なストレス要因に囲まれ、さらには少子高齢化がすすむわが国において、近い将来、動物介在活動・療法の需要が高まることは明らかです。病棟で、患者が特別にトレーニングされた動物と心を通わせている風景のある成熟された将来に向けて、われわれは農と医の両面から準備を進めていく必要があります。担当 動物行動学研究室
講師 松浦 晶央